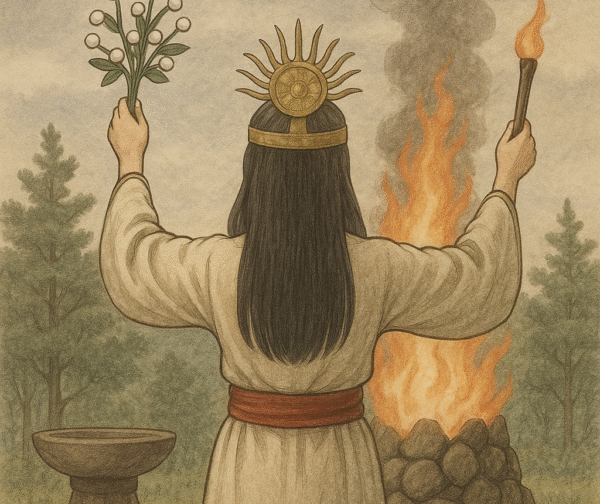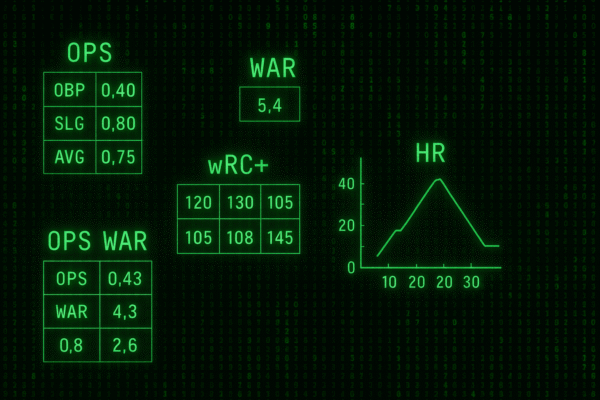日々の疑問をつらつらと。
普段何気なく暮らしていると、
当たり前に或るものや、わかったつもりになっている事には疑問を感じ無くなっているもので。
漫画やアニメや小説の考察は結構前から流行っているけれど、最近は特にブームになっているような気がする。
伏線がかなり敷かれているものや、謎解きは読者に委ねているものなどの考察を見ていると感心するくらい深い。
なんとなく先駆けはアニメ『エヴァンゲリヲン』のような気がする。
キリスト教だけでなくユダヤ教や正典、偽典などの符号を考察していたのだけれど、思わず正解なんじゃないかと感じるくらい。
そんな折り、邪馬台国の歴史に繋がるかもしれない発見があったというニュースを見て、
学校では散々教科書に出てきたこの時代が結構面白い事になっているそうなので、Let’s research.
中国の古書、『魏志倭人伝』にのみ登場する倭国。
倭国では女王が統治する邪馬台国があり、女王の名は『卑弥呼』。
西暦238年に中国大陸の王国、『魏』に使者を送り『親魏倭王』の名称と『金印紫綬』を授かった。
女王は高齢で夫も無く弟を補佐に政治を行っており、30からなる連合国を鬼道(シャーマニズム)をもってまとめていた。
南にある狗奴国とは戦争状態にあり、巫女である卑弥呼が神事を行い、弟が実際の統治を行う二元政治だと考えられているらしい。
邪馬台国の場所は今もはっきりしておらず、畿内説と九州説が有力。
卑弥呼亡きあと男王が起ったが、国が乱れた為に女王『台与(いよ)』が邪馬台国を統治することになる。
日本最古の史書『日本書記』によれば、西暦266年に中国では『魏』から『晋』に王朝が変わっており、『倭』の女王から『晋』国へ通訳を一緒に朝貢したという記述がある。
西暦247年~250年におそらく卑弥呼は亡くなったと思われるが、そのあたりは中国の史書に頼らざるを得ない。
『魏志倭人伝』に寄れば、31の地名と14の官名と8人の人名が出てくる。
音節は当時の日本の発音をもとに漢字を充てたと思われ、『倭』というのもおそらく当時の日本人は自らを『和の国』と呼んでいたのではないかと推測される。
日本語学者の森博達らが古代日本語と特徴が同じであるという指摘があったそう。
ここまではおそらく間違いは無いだろうという話で、ここからは感心してしまった考察を。
日本最古の史書、『日本書紀』と『古事記』。
『日本書紀』は西暦720年、『古事記』は西暦712年に完成。
一応補足として『古事記』のほうは古くから偽書説もあり、完成したのも平安~鎌倉時代ではないかという論説も江戸時代の学者には結構居たそう。
ただどちらも神代~持統天皇、または推古天皇までを記しており、日本国の成り立ちを書いている史書。
この神代の話は史書というより寓話だけれども、何も無いところから出てきた話では無いというのが今回の考察。
『日本書紀』や『古事記』の中に日本の祖とも言うべき神、天照大御神(あまてらすおおみかみ)が登場するが、
この神様は太陽神、皇祖神、巫女の3つの性格を併せ持つ神様であり夫はおらず、ツクヨミとスサノオという2人の弟がいる。
有名な『天の岩戸』の話はスサノオの暴挙に太陽神である天照大御神が岩戸に隠れる話。
代々の天皇家に繋がっていく皇祖神であり、神事を行う巫女。
日の巫女である天照大御神。
『魏』に送った使者はもしかしたら自らの国の女王をそう呼んだのかもしれない。
西暦245年~250年頃に日本では皆既日食か部分日食の可能性が天文学に示唆されているそうで、
『日本書紀』における日本最古の皆既日食の記録は西暦628年、推古天皇の時代だそう。
太陽が消えていく様を間近で見た『日本書紀』を編纂した人達は何を感じたのか。
裏付けも確証も無いけれど、ここまで符号すると全てを信じてしまいそうな今日この頃。