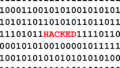日々の疑問をつらつらと。
普段何気なく暮らしていると、
当たり前に或るものや、わかったつもりになっている事には疑問を感じ無くなっているもので。
今日は七夕。
彦星と織姫が1年で唯一会える日で、短冊に願い事を書いて笹に飾り付ける日。
子供の頃はやった記憶はあるけれど、クリスマスや節分と比べるとポピュラーなのに一つ下に置かれているような。
地域のお祭りや学校とかでなければあまり目にしない七夕。
なので今回は七夕をLet’s research
七夕の起源を調べてみるとやはり中国で、"乞巧節(きっこうせつ)"と呼ばれていたものが七夕になったらしい。
中国の神話に由来し、機織りの少女織女と牛飼いの牛郎という2人の恋人のロマンチックな伝説を祝う行事だったとか。
最も古い文献としては2600年前のものの神話に出てくるらしく、
それが日本の江戸時代に輸入されて、日本でも五節句の一つになるほどポピュラーに。
五節句は江戸幕府によって祝日に定められたほど。
ちなみに五節句とは、
人日(じんじつ) 1月7日 一年の無病息災を願う。
上巳(じょうし) 3月3日 女の子の健やかな成長を願う日。
端午(たんご) 5月5日 男の子の成長を願う日。
七夕(しちせき) 7月7日 織姫と彦星の出会いにあやかり、短冊に願い事を書いて笹に飾る。
重陽(ちょうよう) 9月9日 長寿を願う日。
中国では今でも春節にあたる5月5日の端午の節句は盛大に祝うらしい。
春節の時の中国の膨大な人の大移動はニュースでもよく見る。
日本では明治時代に、旧暦が廃止されて新暦を使用するようになってから五節句は廃れたらしい。
それでもひな祭りや子供の日なんかは各家庭で祝う習慣はまだ残っているし、
続けてもらわないと人形屋さんは大変だろうし。
この旧暦というのが厄介で、日付は有名なのに実はズレているというのがミソ。
今年の七夕も実は2025年8月29日(金)。
7月7日だと梅雨最中なので地域によっては8月7日に変えて、星空を堪能出来るようにしている所もあるとか。
中国や台湾ではバレンタインデーに匹敵する行事らしく、織姫と彦星の神話を考えれば当然で、
神話としては機織り上手な女の子と牛飼いが恋に落ちて仕事しなくなったから、
天帝が怒って「会うのは年1な!」とパワハラを決め込んだ話。それくらいベッタリだったのかと。
なのに日本では神事に近くなっていき、織姫の機織りが上手が転じて芸妓の女神様になり牛飼いは空気に。
子供がのびのびと成長するようにと笹or竹に短冊を付けるようになったりとか、
神様なら願い事聞いてくれるでしょと、書いて天に届けたりとか、日本っぽいなぁ。
ちなみにAIに七夕とはなんぞやと聞いてみたところ、
織姫はこと座の1等星・ベガで、彦星はわし座の1等星・アルタイルです。
2つの星の間は14.4光年ほど離れていて、光のスピードでも約14年半かかる距離です。
2人が光のスピードで移動したとしても、1年に1回会うことは不可能です。
・・・。
科学はロマンを破壊し尽すなと思う今日この頃。